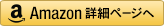「僕にとって定年はない」紳士服業界の重鎮・赤峰幸生が歩む道のり

流行は移り変わる。令和のいま、その流れはさらに勢いを増し、次々とムーブメントが現れては消える。30歳の筆者でさえ目まぐるしいと感じるほどだ。
そんな激流のような世界でとても自然な佇まいを見せ続けているのが、紳士服業界の第一線で長年活躍してきた赤峰幸生氏だ。
赤峰氏は、お客さんからオーダーが入るとまず“問診”から始めるという。まずは出身地、人柄、生活の様子などについて会話をする。服に触れるのはそれからだ。それはいったいどういうことなのか? それは赤峰氏の人生を遡っていくと答えが見えてくる。
流行を追いかける手を一旦止めて、改めて自分が選ぶべきものはなんなのか。赤峰氏の人生を追うとともに、ぜひ思いを巡らせてみてほしい。

- 赤峰幸生(あかみねゆきお)
インコントロ代表。数々のメンズブランドを手がけ、クラシック業界の第一線で活躍し続ける。
1998年に紳士服ブランド『Y.Akamine』、2008年にカスタムクロージングブランド『Akamine Royal Line』を立ち上げる。
日本を大きく変えたアメリカンカルチャーの到来

本日はよろしくお願いいたします。紳士服界の大御所である赤峰さんですが、衣服に関心を抱いたきっかけを教えてください。
赤峰幸生(以下、赤峰)
どなたにも思春期ってあるじゃないですか。僕はそういった年ごろのときに、自然と衣服に関心を持ち始めました。そして渋谷にある『桑沢デザイン研究所』に入学し、デザインの基礎を学びました。

当時は、パリのオートクチュール界が活況の時代だったんです。クリスチャン・ディオール、ココ・シャネル、クリストバル・バレンシアガといったデザイナーたちが一線を風靡していました。僕ももれなくその世界に憧れて、毎日デッサンを描いていましたね。
学校を卒業したあとは、日本オートクチュール協会にいらっしゃったジョージ岡氏に弟子入りし、婦人服の基礎を学びました。雑巾掛けから雑用まで、まさに丁稚奉公のような感じです。2年半ほど修行をさせていただいたのちに、婦人服から紳士服業界に進みました。
当時はどういった紳士服を作っていたんですか?

赤峰
最初に勤めた会社では、ワークウェアを作っていました。昔は足袋などを作っていたのですが徐々に売れなくなり、ワークウェアに移行し始めたんです。当時の日本は、アメリカの文化が急激に広まった時代でした。“カジュアルウェア”というジャンルもそのころに生まれたんです。
衣服だけではなく、マクドナルドの1号店が誕生したり、コカ・コーラやペプシコーラが販売されたり、バンホーテンココアが登場したり、スーパーマーケットが誕生したり、ありとあらゆるものがアメリカナイズされていったわけです。あとは“ジーンズ”ですよね。アメリカの軍服や作業着も米軍基地から横流しされ、国内にどんどん広まっていきました。
そのころファッションはどういったものがブームだったんですか?

赤峰
紳士服でいうと、「Brooks Brothers(ブルックスブラザーズ)」というアメリカのブランドが人気で、みんなの憧れでした。1950年〜60年代には、石津謙介さんというデザイナーの方が「VAN」というブランドを立ち上げ、“ヴァンヂャケット”ブームを生みました。その後も石津さんは、ボタンダウンシャツやローファーを着用する“アイビールック”というファッションブームも生み出しましたね。
僕は当時お金もなかったので、ひたすら観察して外国文化を学んでいました。いまのように携帯もなかったので、自分の足で見て回り、知識を吸収するしかなかったんです。『AMERICAN PHARMACY(アメリカンファーマシー)』という薬局があるのですが、そこにはボタンダウンタイなど、いままで見たこともなかったアメリカのものがたくさん売っていました。『帝国ホテル』では、ナイフとフォークを使って食事をしている外国人を、指を咥えながら見ていましたね。
日本のカルチャーの変革期だったんですね。
赤峰
そうですね。その後はまた別の紳士服メーカーに勤めました。その会社では、商品の8割をアメリカに輸出していたんです。そこでは“大量生産・大量消費”のシステムを学びました。現代のファストファッションブランドの先駆けのような感じですね。そして28歳のときに、独立をしました。人生で初めてとなる「WAY-OUT」というブランドを立ち上げたんです。
「段取り八分、仕事二分」

組織に属するのではなく、独立の道を選んだのには理由があるのでしょうか?
赤峰
会社員だと60歳を過ぎ定年を迎えると思うのですが、僕にとっての定年は“死んだとき”なんです。定年後に悠々自適な生活を送っている方もいると思うのですが、僕は自分のなかの意欲が高まるものを追い求め、そのためにどういった段取りを組んで毎日を過ごすのか。そういった張り合いのある人生の方が好きなんです。
生きるということは、“ある一定の負荷”を自分にかけることだと思います。ストイックにジム通いをする、ということでもないんですけど、僕は常に着たい服を着続けられるようにありたいと思っているので、料理や運動など、そのためには何をしたらいいのかを考えながら日々を過ごしています。
常に何かしらの目的を持って生きていくことが大事なのですね。
赤峰
「段取り八分、仕事二分」という言葉がありますよね。風が吹けば桶屋が儲かるじゃないですけど、僕はいつも頭のなかでぐるぐる考えながら過ごしているんです。段取りを考えることが好きっていうのもあるんですけどね。たとえば料理でいうと、作るのに1時間かかっても、食べるのは10分かそこらじゃないですか。食べるまでの段取りが勝負。
生きるうえでも、そこを考えるのがいいんですよ。毎日ダラっとテレビを見て過ごしていたら、それこそ死に向かっています。足が動く限りは歩いて季節を感じたり、美味しいものを食べに行きたいですしね。そういう”意欲”が僕を動かすのです。今年で80になるのですが、「まだ80か」と思っていますよ。「俺も年だしな」とはあまり思わないですね。
そんな赤峰さんが影響を受けた人物はいますか?

赤峰
映画監督の小津安二郎さんが書いた「老いの流儀」という書籍があるのですが、感銘を受けましたね。フランスでも人気の映画監督なのですが、自分のスタイルや生き方が詰まっていて、大きく影響を受けました。僕は服の仕事をしていなかったら、映画監督を目指したかったくらい映画も好きなんです。フランス、イタリア、スウェーデンなど、1930年代ごろのいろんな国の映画を見て、たまにクラシックスタイルの原点に立ち帰ります。
イタリアで知る万物の“ルーツ”

赤峰さんが初めて立ち上げた「WAY-OUT」とは、どういったブランドなのでしょうか。
赤峰
当時、紳士服の王道は先ほども申し上げた“ヴァンヂャケット”でした。その王道に対して、「WAY-OUT」はその外。王道ではないが、日本人のためのクラシックなスタイルを確立したのが「WAY-OUT」なんです。これは僕がクラシックの服作りを追い求めるきっかけになった瞬間でしたね。
人生初のブランド立ち上げ。苦労も多かったのではないでしょうか。
赤峰
2人で立ち上げたのですが、まあ大変でしたね(笑)。1LDKのマンションを借りて、中古のハイエースを買いました。車に目一杯商品を積んで、広島から京都、名古屋まで商品が空っぽになるまで走り回りました。兵庫県の西脇市というシャツ生地の産地があるのですが、帰りにそこで仕入れも済ませて、また車をパンパンにして帰ってきました。
真冬は寒いんですけど、眠くてね。窓を少し開けながら走って、疲れたら側道に止めて少し休んだりして。大変ではありましたが、あの体験がいまのエネルギーの原点になっている気がします。体力もそうですが、精神的な強さの基盤がそこでできたと思います。

素敵な思い出ですね。赤峰さんは、その後もいくつかブランドの立ち上げをされましたよね?
赤峰
34歳のときに生地屋の社長から連絡があって、服を作って欲しいと依頼されました。そのときに立ち上げたのが、「GLENOVER(グレンオーバー)」です。グレンというのは、スコットランドで“渓谷”という意味があります。渓谷を超える、という意味を込めて「GLENOVER」という名前をつけました。
そして、そのころはよくイタリアに行くようになりました。全部合わせたら400回くらい行ったんじゃないかな。イタリアは20の州でできているのですが、そのうち19の州を訪れました。イタリアの国土面積は日本とほぼ一緒なんです。いろんな土地を回りましたが、イタリアの服が好きだから訪れていたわけではないんですよ。イタリアは歴史が古く、洋服はもちろん食べ物や文化、いろんなもののルーツが辿れる国でもあるんです。
たとえばコーヒーのエスプレッソってありますよね。そもそもコーヒーはトルコで生まれ、その後イタリアで広まり、ヴェネチアにある『カフェフローリアン』を筆頭にエスプレッソが広まっていきました。そういったルーツを辿るのが好きなんです。何事も派生する前の“本来”の状態があるじゃないですか。そのルーツの根元にたどり着いたときに、すごく喜びを感じるんです。
歴史が深いイタリアは、まさにルーツの宝庫ですね。衣服も、歴史や背景を知った上で着るのと、何も知らないで着るのではかなり違ってきそうです。
赤峰
日本の衣服の歴史は、170〜80年ほどしかありませんからね。さまざまな歴史を学び、洋服の仕事を通して、そのルーツをみなさんにお裾分けさせていただくことが、いまの僕の役割だと思ってます。

2008年には「Akamine Royal Line」というカスタムクロージングブランドを立ち上げられたかと思うのですが、こちらはどういったブランドなのでしょうか?
赤峰
イタリアであらゆるもののルーツに触れたからこそ生まれたのですが、日々の暮らしに密接しているブランドになります。お客さま一人ひとりに向き合って服を作らせていただくのですが、衣服のこと以外にも、お客さまがどういった暮らしをしているのか、どんなことを知りたいのか、お客さまのルーツを知ってから制作に入らせていただきます。
まさしく赤峰さんの人生観そのものがかたちになっているということですね。現在赤峰さんは、YouTubeやInstagramでも活発に活動されていますが、現代のSNSについてはどう考えていますか?
赤峰
自ら新しいことを取り入れたいという思いはそこまでないんです。ただ、こういうふうに生きている男もいるよ、ということをただ勝手に発信しているだけなんです(笑)。時代はどんどん変わっていくじゃないですか。その流れに対して逆らうつもりもないし、迎合するつもりもない。自然に生活しているなかのひとつ、という感じですね。

どんなカルチャーでもルーツを辿ると、思ってもいなかった一面を知ることがある。だが衣服はとくに、表面上だけに着目してしまいがちだ。
「このブランドを着てるとかっこいいから」「この服の方が好かれそうだから」「この組み合わせが流行っているから」というような理由で服を選ぶことは正直多い。ただそういった理由で選んだ服は、本当の自分に合っているかどうかが置いてけぼりになっている気がする。
いろんなもののルーツを知るということは、自分のルーツも知ることなのではないだろうか。身につけるもののルーツと自身のルーツがマッチしたとき、それはきっとかけがえのない1着になるのだろう。ただ消費する布ではなく、“愛”を持った大切な衣服になるかどうかは、そこが分岐点になっているのかもしれない。そしてその深みを持ったものに囲まれている方が、絶対に人生は楽しい。
赤峰幸生氏インフォメーション
この記事について報告する