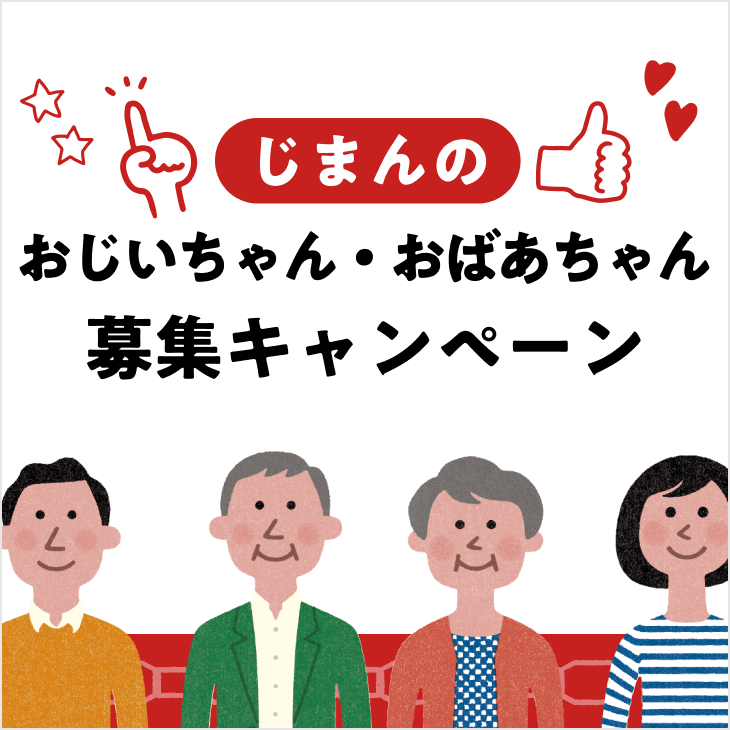写真家・舞山秀一【前編】
シャッターを切ることの責任、進化し続ける理由

広告、CDジャケット、雑誌、写真集などで、あらゆる著名人を撮影している舞山秀一さん。これまでに撮影した雑誌の表紙は130点以上、CDジャケットは350点以上にも及ぶ。独立から36年、今年60歳を迎えた舞山さんの写真家人生を紐解くインタビュー前編は、プロとして独立するまでの経緯、写真家としてのポリシーと、舞山さんにとって重要なキーとなる「旅」の原点について話を聞いた。

- 舞山秀一
1962年、福岡県生まれ。1986年に独立し、ポートレートを中心に広告、CDジャケット、雑誌、写真集などで幅広く活躍。また、作家としても個展を定期的に開催し、作品集も出版している。第22回APA展にて奨励賞受賞。2004年より日本広告写真家協会・正会員。2014年より九州産業大学芸術学部客員教授就任。

高校の写真部から大学の写真学科へ
写真を始めたのは高校時代で、写真部で部長を務めていたそうですね。その時にはもうプロを目指していたのでしょうか?
舞山
いや、まさか(笑)。高校がデザイン科で、色彩構成や平面構成から始まって絵を描いていて、元々は美大かデザイン科のある大学に進学する予定だったので、高2の時から進学コースでデッサンばかりしていたんです。美大の試験ってデッサンがメインなので。だけど、写真部にいたのもあって色々な写真を見るようになったら、憧れる人が何人も出てきて、やっぱり写真科に行こうと高3の夏くらいに進路を変えたのかな。それで推薦枠に入ることができました。
九州産業大学芸術学部写真学科に進学後、プロとしてやっていきたいという思いが徐々に芽生えていったのでしょうか?
舞山
僕は漠然と、写真科に行く=写真家になるという腹積りだったんだけど、周りの友人たちの中でそんなことを思っているヤツは本当に少なくて。意外や意外、写真の方向に進んだのは本当に一握りです。約130人同じ学部学科に入ったのに、卒業したのが約70人、その中で写真家を目指して東京に出たのが5人、その内2人は下積みだけして田舎に帰りました。今、その母校で客員教授として教えていますけど、やっぱり毎年、東京に出るのは多い時で5人、少ない時は2人か3人ですね。但し、写真専攻の人数自体が昔ほどは多くないですけどね。
在学中に気持ちが変わるのか、何か現実を見るのか、どういう現象なんでしょうね。
舞山
例えば経済学部に行く人は、全員が経済学者になりたくて行くわけではないじゃないですか。法学部に行く人は、全員が司法試験を受けて弁護士や裁判官になろうとしているわけじゃない。就職率が良いとか、法律に興味があるから学びたいとか。それと同じ次元に写真学科もあるんですよね。
なるほど。
舞山
昔はフィルムを覚えて、現像を覚えて、プリントできて、光や露出のことを勉強して、全てちゃんと身に付けないとカメラマンになれなかったから、そういうことを学びに来ていたはずなのに、今はカメラが全部やってくれるから、必要なのはセンスだけになったんですよ(苦笑)。それをどう磨くか、鍛えるかは、言っちゃ悪いけど街のカルチャーセンターの延長に近いのかなと思う。学生を見ていても、写真そのものには皆真剣だけど、写真家を目指すということに真剣なのは全体の1割か2割しかいないです。僕はそれを3~4割に伸ばすために行っているんだけどね。

スタジオマン、アシスタントを経て独立
舞山さんは1984年に大学を卒業後、スタジオエビスに入社、半沢克夫さんに師事、そして1986年に独立したということで、かなり早い独立ではないかなと思うのですが。
舞山
スタジオマン時代もアシスタント時代も、今の2倍は濃厚な時間を過ごしていたと思います。スタジオマン時代は月200時間くらい残業していたし、アシスタント時代もほぼ休みなく働いていて。アシスタントが僕一人だったので、北海道にロケに行ったら翌日ハワイに行って、戻ってきたらヨーロッパ、戻ってきたら九州…みたいな。その頃、うちの師匠が本当に忙しかったので。だから一気に濃密に下積みをしたせいで、もういいかなとなったんですよね。
確かにそれはものすごい密度です。
舞山
入った瞬間から1st=アシスタントが僕一人しかいなかったんですよ。もしも2nd、3rdまでアシスタントがいたら、3rd、2nd 、1stそれぞれ2年ずつやって計6年とか4年で卒業していたかもしれないです。逆に言えば、アシスタントが5人いると卒業するのに10年かかるんです。そういう時代だったんですよね。まぁ2年は確かに早かったと思いますけど、最初からフィルムの管理、露出をとって現像してプリントまでの作業を一人で全部手伝っていて、何なら打ち合わせも一緒に連れて行ってもらって、ノウハウまで全部見せてもらったので早かったということですね。

全責任を背負ってシャッターを切る
舞山さんは広告、CDジャケットや雑誌、作家としての作品など様々な形で写真を撮影していますが、それぞれに臨む時の心構えとして、共通している点と異なる点は?
舞山
共通しているのは、どれもやり直しがきかない。僕がやっているパートだけじゃなく結婚式の撮影だってそうだし、写真を生業にしている人はやり直しがきかないことがほとんどなので、そういう緊張感があります。プロの場合は「ごめん、イマイチだったからもう1回撮らせて」というのはできないから。お金がかかっている分、絶対に失敗できないという責任があります。今はデジタルだから、横でアートディレクター、ヘアメイク、スタイリストもモニターを見ていて、オールチェックしながら撮っているけど、昔はシャッターを切る人の全責任だったわけ。シャッターを切ったからには、洋服が捲れていても「なぜ捲れているって言わなかったの?」と言われちゃうし、ヘアメイクが良くないと思っても「なぜ現場で言わないの?」って言われる。表情が良い悪いも、天気さえもこちらの責任。
え…!?
舞山
本当なんですよ(笑)。天気が悪くてあまり良い写真にならなかったとしても、天気のせいにはできなかったの。「良いと思ったからシャッターを切ったんじゃないの? 『天気が悪いから撮れない。もうちょっと待とう』って言えば良かったじゃん」とか、「なぜお日様が照っているようなライティングにしなかったんだ?」と言われるんです。
本当に全責任を背負っていたんですね…。
舞山
今は横にモニターがあって、撮った端から「わー、すごく可愛い!」とか言われながらやっていて(笑)。僕らは「いや、ちょっと待って。今のはダメだよ。後で怒られるのは俺だから」という感じでやってきましたけど、今の撮影環境は「良いって言ったじゃん」と言えるから、責任が半分くらいになっているのかも。ヘアメイクさんもスタイリストさんも「わー、可愛い! カッコいい!」って、モデルをのせるために言ってくれるわけ。だけど、本当にカッコいいかどうかは自分がジャッジしないと後で後悔する。そういう責任はどの写真にも共通している点で、共通しない点は…あまりないんですよね。1万円の仕事も100万円の仕事も同じスタンスでやっているから区別はしていない。だって、どの仕事も俺がやった仕事だから。そういう意味で言うと、全然手を抜かないです。仕事としてやるものは全て一緒ですね。

常に110、120点を目指していないと次はない
舞山さんは一度やったことは二度やりたくないというのがポリシーだそうですが、それはプロになった当時からでしょうか?
舞山
ある程度の仕事ができるようになるまでは不安はあったし、繰り返すようなこともあったかもしれないです。でも、仕事をしているうえで、傍からは繰り返しているように見えたとしても、少しでも変化していないとダメだなとは思っていました。先ほどの話のように、皆が「いいね!」と言うわけ。それで「こないだのと同じようにやって」と言われたりする。でも、こないだのことは僕が提供した新しいアイディアだったりするから、皆が「おっ、スッゲー! 舞山さんすごいですね!」と褒めてくれて、その時は皆の期待が100だとしたら、120の答えを出しているんですよね。次に同じことをやると、皆が知っていた100でしかないから、その100を超えることは絶対にないです。「期待通り。安心だね」とは言われる。だけど、その次は多分違うカメラマンになっているよ。
厳しい世界です。
舞山
大元の絵コンテがあって、それを化けさせたから皆、衝撃を受けたわけで、「こないだと一緒でやってくれ」と言われて本当に同じにやったら、今度はどちらかと言うと評価が下がるんですよね。絶対にそこで変化させていないと、120点にはいかない。だから常に110、120を目指していないと、皆がビックリすることにはならないし、やっぱり頼んで良かったとはならないんですよ。そういうのを20代から始まって何度も経験して。僕がよく言うことで、アーティストは去年と同じ曲も歌うけど新曲も出すし、ファッション業界は半年に1回、コレクションを総入れ替えする。それって去年と同じなんてことはないじゃないですか。俺の周りはずっと進化し続けているのに、俺だけ同じじゃあり得ないなと。同じことを提供しているんじゃ、クリエイターとしては失格かなと思う。
ものすごく納得です。
舞山
ハイブランドでいたいか、量販店でいるのかの違い。自分がどうありたいかの差ですね。

旅好き少年とカメラマンの出会い
舞山さんにとって旅は切っても切り離せないものだと思いますが、意図的に創作に活かすために旅をしているのか、元々旅が好きで後で振り返った時にそういうものになっていると気付いたのか、どちらでしょうか?
舞山
今回(11月22日~12月3日開催の「舞山秀一写真展 [Drift] A Moment2022」)の旅のシリーズを展示するに至ったのも、ちょうど『Cameraholics』という雑誌から旅をテーマに写真を出してくれないかと言われて、撮りっぱなしで人に見せていないシリーズがあったなと引っ張り出して見ていたら、これはいいなと思って展示することにしたんですよ。その時に、旅について原稿を書かなきゃいけなくて、すごく考えて、自分の旅のベースを紐解いてみたんです。それで、小学生の時に旅番組が死ぬほど好きだったということを思い出したの。写真より先に旅が好きで、僕の憧れは海外を旅することだったわけ。そういうのが根っこにガッツリあったんです。
そうだったんですね。
舞山
小学校の5年か6年の修学旅行の時に、初めてカメラマンに出会いました。遠足とかについてくる人がいるじゃないですか。その人に「どうやったらカメラマンになれるんですか? カメラマンになると、いつもこうやって旅ができるんですか?」って聞いたのを覚えています。そしたら「年中旅しているよ。あちこちの学校と色々なところに行くよ」と言われて、「いいなぁ! カメラマンになったら旅ができるんだ!」と思って。それがカメラマンに触れた本当の最初。どうやったらカメラマンになれるのか聞いたら、その人は東京の専門学校を出たと言っていて、そういう学校があるのかぁと。
子供の頃に意外な方向からカメラマンとの接点があったんですね。
舞山
そうなんです。憧れの筆頭ではなかったけど、一部にはもうなっていたのかもね。中学生になってからは全くそんなことは考えもせず。ただ僕、天体や宇宙にも興味があって、星が好きだったんですけど、親父のカメラを借りてはフィルムで北斗七星とか星座を撮っていたのを思い出しました。子供の時から夢見がちだったんですよね(笑)。
インタビュー後編では、旅がもたらしたターニングポイント、時代の流れとともに様々な変化があった撮影の仕事とそこで得たもの、さらに今後について伺います。
後編記事はこちら→ 写真家・舞山秀一【後編】業界の変遷と自身のターニングポイント
舞山秀一 写真集はオフィシャルサイトから購入可能
この記事について報告する