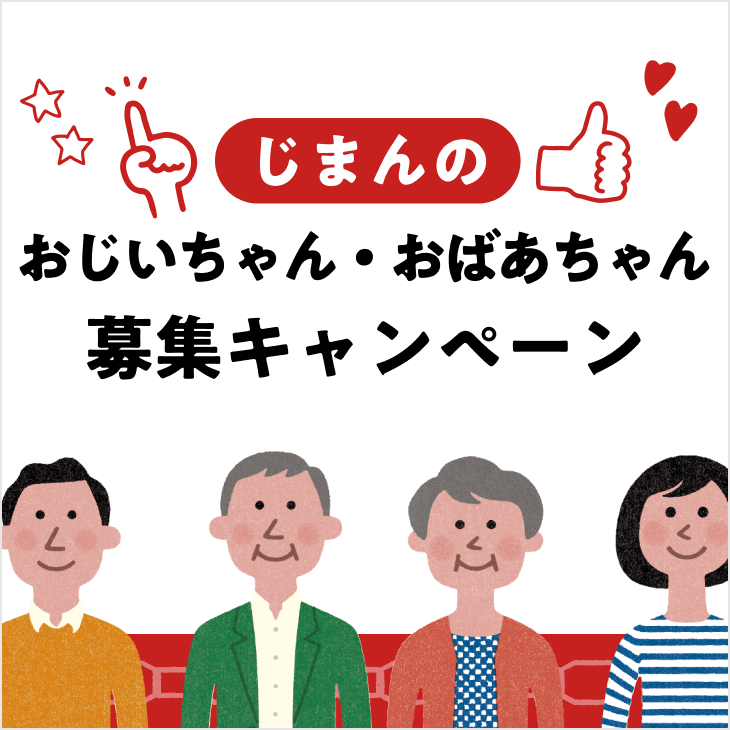リンボウ先生インタビュー(後編)「後ろから迫ってくる死」の迎え方

エッセイスト、小説家にして、国文学者、書誌学者でもあるリンボウ先生こと林望(はやし・のぞむ)さん。その他には、バリトン歌手、イラストレーター、歌曲の作詩家、能作家などの顔も持つ「多芸多才の人」である。
そんなリンボウ先生の最新刊『定年後の作法』(ちくま新書)は、定年後のセカンドライフを豊かにするための提言がしたためられているだけでなく、自らの「人生の片づけ方」についても大胆に言及されている。
そこでインタビュー後編では、本の内容にからめて先生の死生観について探っていこう。
前編記事はこちら→リンボウ先生インタビュー(前編) 「思い通りにいかない人生」との付き合い方

- 林望(はやし・のぞむ)
1949年生まれ。作家・国文学者。慶應義塾大学大学院博士課程修了。 ケンブリッジ大学客員教授、東京藝術大学助教授等を歴任。『イギリスはおいしい』で日本エッセイスト・クラブ賞、『ケンブリッジ大学所蔵和漢古書総合目録』で国際交流奨励賞、源氏物語の個人全訳『謹訳 源氏物語』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。エッセイ、小説の他、歌曲等の詩作、能楽、自動車評論等、著書多数。
「人生の店じまい」を意識したきっかけ
ライフワークである『謹訳 源氏物語』の仕事を終えて、燃えつき症候群のような虚脱感に襲われるようなことはありませんでしたか?
林
幸いなことに、それはなかったです。本が刊行されれば、それをできるだけ多くの方に知ってもらうために講演や朗読会などに奔走していましたので、それなりに忙しい日々でしたから。
もちろん、訳業の途中から、この仕事が人生最後の大仕事になるだろうという予感はありました。私の人生で3つ目の大仕事です。
ひとつ目の大仕事は、30代のときに手掛けた『ケンブリッジ大学所蔵和漢古書総合目録』です。それが、どれだけ大変な作業だったかは、前編のインタビューでも少し話しました。
ふたつ目の大仕事は、50代の前半を費やして完成した『薩摩スチューデント、西へ』(光文社)という歴史小説です。維新前夜1865年に薩摩藩が極秘裏にイギリスへ送った、俊英留学生15人と秘密使節4人の群像劇です。
小説とはいえ、史実を描くわけですから、集められる限りの資料を集め、読み込み、実際の舞台になった場所について研究しましたが、それらの準備に6年もかかりました。
そして、みっつ目の『謹訳 源氏物語』という大仕事を終えたとき、今後同じようなスケールの仕事を手掛けるような気力、体力はもう残っていないだろうと見積もったのです。
作家には定年はありませんが、ある意味で定年に似たような心境になったわけです。そろそろ人生の店じまいの支度をしなければならない、と。
書物は「価値のあるもの」から手放す
人生の店じまい、というと、どんなことをするのですか?
林
もともと私は60歳を過ぎたころから、極力物を買わず、身辺の物を増やさないように努めてきました。物に対する欲望を捨て、生活コストを低く抑える努力です。
ただ、書物について言えば、話は別です。作家、研究者にとって、生活の基盤となる書物は、どうしても座右に備えておかねばなりません。いちいち図書館に通って調べたりしていては、時間がいくらあっても足りないからです。
その結果、自宅の地下室にある書庫には、約2万点の蔵書が溜まっていました。
健康を害するなどして著述業を廃業するか、死のギリギリまでこれらの書物を手元に置いておくというのは、あまり良い選択ではないように思われました。
なぜなら、本の価値を知っているのは私だけですから、家族に処分をまかせるとなると、二束三文で売られるかゴミとして捨てられるかでしょう。ですから、私が元気なうちにこれらを正当な評価のもと、古書市に出したり、しかるべき機関に買い取ってもらうのが賢明であると判断したのです。
まず私は、「価値のある書物から手放す」という方針を立てました。

書物の目録作りをするには「人生が足りない」
「価値のある書物」というと?
林
たとえば、『古文真宝(こぶんしんぽう)』という書物があります。中国の漢代から宋代までの文献を収めたアンソロジーのような書物です。
漢詩を集めた「前集」と名文集である「後集」に分かれていて、特に「漁父辞(ぎょほのじ)」とか「帰去来辞(ききょらいのじ)」といった昔の人の一般教養になっていた名文が網羅されている「後集」は、これさえ読めば一応わけ知り顔ができる書として人口に膾炙(かいしゃ)しました。
だいたい、室町時代末期から江戸時代の全体、それから日本の近代化が完成する明治20年あたりまでの約300年の間に盛んに流布し、西鶴も芭蕉も、あるいは近松も、この書物をもって基礎教養としたのです。
ですから、実に膨大な『古文真宝』がこの世に存在します。今でも神田あたりの古書店に行けば安いものは数千円くらいの値段で買うことができますが、それくらい「ありふれた」書物であっても、「ありふれた」からこその価値というものがあるんです。
というのも、それだけありふれているということは、それだけ多くの読者をもち、文化的に大きな存在であったということです。このことは私の師匠阿部隆一先生のご見識でした。
私は大学院生時代から、40年に渡って約2000冊の『古文真宝』を集めましたが、買っても買っても、同じ刊記を持った同版同印の本というのは、ほんとうに少ないのです。つまり、『古文真宝』は書誌学的に見て、日本の出版史を物語る格好の資料なんですね。
ですから、大学共同利用機関である国文学研究資料館が買い取ってくださるというので、委譲することにしました。
大事なコレクションを手放すのは、身を切るような思いだったのでは?
林
実は、『謹訳 源氏物語』の仕事を終えたとき、この『古文真宝』の目録を作ろうかと考えたこともあるんです。
たとえ同じ版木によって刷られた本だったとしても、刊記や奥附がどこか違っているとか、刷りの状態が早いものと遅いものの違いがあったりして、あたかも壮大なジグソーパズルの一つひとつを埋めていく作業ですが、『古文真宝』が約2000冊も集まっているのは世界唯一のことですから、目録があればその価値を最大限に引き出すことができます。
でも、それをなし得るには「もはや私の人生では足りない」と判断せざるを得ませんでした。そこで、国文学研究資料館の研究材料にしてもらうことにしたのです。
書物は個人の所有物ではない。世間にお返しすべきである
書物の価値を知っていればいるほど、「価値のある書物」を手放すのはむずかしいのではないですか?
林
なに、いったん手放してしまえば、あまり未練は感じないものです。
和書の寿命は長く、保存さえよければ1000年でも命を保ちます。奈良時代に写した写経などを見ても、昨日写したのではないかと思うほど鮮明で美しいものがあります。
欧米の書物には多く羊皮紙とインクが用いられましたが、羊皮紙は動物性タンパク質ですから劣化が早いし、インクも酸化すれば消えてしまいます。それに比べて和紙に墨で書かれた和書は、非常に安定な物質でできているのです。
ひとりの人間の命は、たかだか90年くらい。書物の1000年以上の寿命と比べれば、知れたものです。となれば、祖先が残してくれた文化財である書物を自分の所有物であると考えるのは思い上がりというものです。
つまり、書物を手放すということは、しかるべきときに、しかるべき正しい手段で世間にお返ししていくことにつながるのです。

死は前からやって来るのではなく、いつの間にか後ろから迫って来る
「人生の店じまい」は、最後にやってくる「死」をいかに迎えるかという準備になると思いますが、それについてはどう考えていますか?
林
吉田兼好の『徒然草』第百五十五段に、次のような言葉があります。
「死は前(まへ)よりしも来らず、かねて後(うしろ)に迫れり」
死というものは、前のほうから、あ、死があそこからやって来たなと目に見えるような形で来るのではない。いつの間にか、ひたひたと背後に迫って来ているのである、というわけです。
恐ろしい言葉ですね。実際、私も死についてただひとつ確定できるのは、「死は不確定である」ということしかないと思います。確定的に語ろうとすれば、パラドックスが生じてしまうものなのです。
でも、私は自分の死について、あまり悲観的に考えてはいません。
それは、なぜですか?
林
すでに物故した私の両親が、良い手本を示してくれたような気がするからです。
母は64歳のときにがんを発症し、72歳で亡くなりましたが、最期はホスピスに入っていましたから痛みや苦しみは最小限に抑えられていて、おだやかな死でした。
がんに罹ってからの8年間を家族や親類縁者、友人、知人らとのお別れの期間だったと考えれば、「がんで亡くなる」ということは、兼好法師の言う「前からやってくる死」と同じだと言えるかもしれません。母はそのことを、身をもって私に示してくれました。
だんだんと縮んでいくようなおだやかな死
お父さんは、どんな風に亡くなったのですか?
林
父は、母と違って病気ではなく、直前まで元気にしていて、95歳の晩秋、ふと眠ったきり、そのまま安楽に大往生を果たしました。
父は経済企画庁の官僚エコノミストや東京工業大学の教授職を経て、トヨタ財団の専務理事、東京情報大学の学長、日本財団の特別顧問といった要職についていたことは前編のインタビューでもお話しましたが、母が亡くなる3年ほど前にはすべての職から退き、母の看病に専念していました。
ですから、母が亡くなったとき、父はそれほど悲しんだ様子ではありませんでした。おそらく、母が8年に及んだがんとの闘病から解放されたことを喜ぶとともに、「夫として妻にやれるだけのことはすべてやった」と思っていたからでしょう。
葬儀も、葬儀会社の人が「私も長年、葬儀屋をしていますが、こんなににこやかな葬儀は初めです」と言ったほど、涙と無縁の式でした。
ですから、母が亡くなったあとの父は、心身ともに元気そうでした。ゴルフとかテニスなどのスポーツには一切興味を持ちませんでしたが、足が衰えたら人間ダメになると言って、毎日自宅の近所をよく歩き、ときには一人でふらっと電車に乗って、都心に遊びに行ったりしていました。
それが93歳になると、自宅がある小金井と吉祥寺くらいまでの10㎞圏内になり、94歳になると自宅から駅までの数㎞圏内に行動範囲が狭まっていきました。
若いころは世界中を飛び回って活動していた父も、次第に外国への足は遠くなり、90歳を過ぎてからは「都内から近在へ」、「隣町から家の周囲へ」という順番でだんだんと縮んでいく、それが自然の摂理なのだと、父はその死に至る道筋を見せてくれたわけです。
無論、母のように死にたい、父のようにして死にたいと願っても叶う当てはないわけですが、死が必ずしも恐怖や苦痛を伴うものではないということを、私は身近にいる両親から学んだつもりです。
人生に未練を残さない、潔い死に様
ところで、先生は謹訳シリーズの第2段である『謹訳 平家物語』を著した際、この物語を「死の万華鏡」、「死に様コレクション」と称していますね。この物語の中で印象に残っているのは、どの人物の死に様ですか?
林
確かに『平家物語』は、いろいろな人たちの死を描いています。それは、琵琶法師が非業の死をとげた平家の人々の魂をなぐさめるため、すなわち、祟らないようにするために語った物語だからです。
独裁者として圧政を行った平清盛と、清盛とは逆に、正しい人として描かれた息子の重盛の死に様はおとぎ話じみていて、あまりリアリティがないんですが、源平合戦で果敢に闘った人たちの死に様はリアルで魅力的です。
中でもひとり、印象深い人物を挙げるとすれば……、そうですね、平家の軍勢を率いたリーダー、知盛の死に様でしょうか。
戦いに決着がついたとわかるや、「見るべき程のことは見つ」と言って、鎧二領を重しにして壇ノ浦に入水するわけですが、そんな風に人生に未練を残さない死に様は、実にカッコいいなぁと思います。

理想は「恬淡」と年をとっていくこと
最後に、読者に向けて「理想的な年のとり方」について、アドバイスしていただけませんか?
林
肝心なのは、「恬淡(てんたん)としていること」だと思います。無欲で、物事に執着せず、つねに心をあっさりと安らかにしておくということ。
日本では、4年後の2025年に私を含む「団塊の世代」の人々が、75歳以上の「後期高齢者」になり、超高齢化した社会の仕組み作りが急がれています。
戦後の第一次ベビーブーマーである団塊の世代の人たちの特徴は、学校への進学はもちろん、社会に出てからの立身出世をめぐる競争相手が多く、集団生活の中でガツガツと我を張ることをよしとするところがあります。
そんな中で、そういう集団生活的競争に加わらなかった私は、つねに異端でした。学校での修学旅行や林間学校などの団体行動は、苦痛でしかなかった。
イギリス留学をしていた当時のケンブリッジには「ザ・ソサイエティ・フォー・ジャパニーズ・スコラーズ」という、日本から来ている先生たちの親睦団体があったんですが、私は1度顔を出しただけで時間の無駄だと覚って2度と行きませんでした。あとで聞いた話によると、「林という奴は、ひどく偏屈な男だから近づかないほうがよい」と噂されていたそうです。
これは私としてはもっけの幸いで、向こうのほうから敬遠してくれれば、余計な人間関係に煩わされずに仕事に没頭できますので、むしろありがたかった。
ガツガツとした生活に慣れていくと、「恬淡」との距離がどんどん遠くなっていきます。「定年になったら生き方を変えよう」などと思っていても、なかなかそれを実行できず、つねに満たされない欲望に惑わされてしまう。
ですから、なるべく早いうちからおだやかで安らかな「恬淡」の道に進む準備をしたほうがいいと思います。早ければ、早いほどいいですね。
大変、有意義なお話、どうもありがとうございます。
林
いえいえ、どういたしまして。


好評発売中!
林望・著『定年後の作法』(ちくま新書)
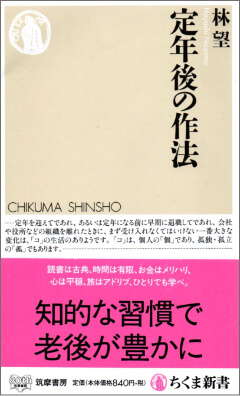
- 著者:林望
- 出版社:筑摩書房
- 発売日:2020年12月7日
- 定価:924円(税込)
まだ老いていないから元気。
しかも会社にいかなくてもよいから疲れることもそんなにない。
でもその力の使いどころを間違えると、悲しい定年後を過ごすことになってしまう。
話が長かったり、過去の栄光にしがみついたり、下手の横好きにお金をかけたりすると、
まわりから嫌がられるに違いない。
そんなことにならないために、自分を律し、先を見据えた生き方を学ぶ必要がある。
人生百年時代に必須の一冊。
筑摩書房 定年後の作法 / 林 望 著
この記事について報告する