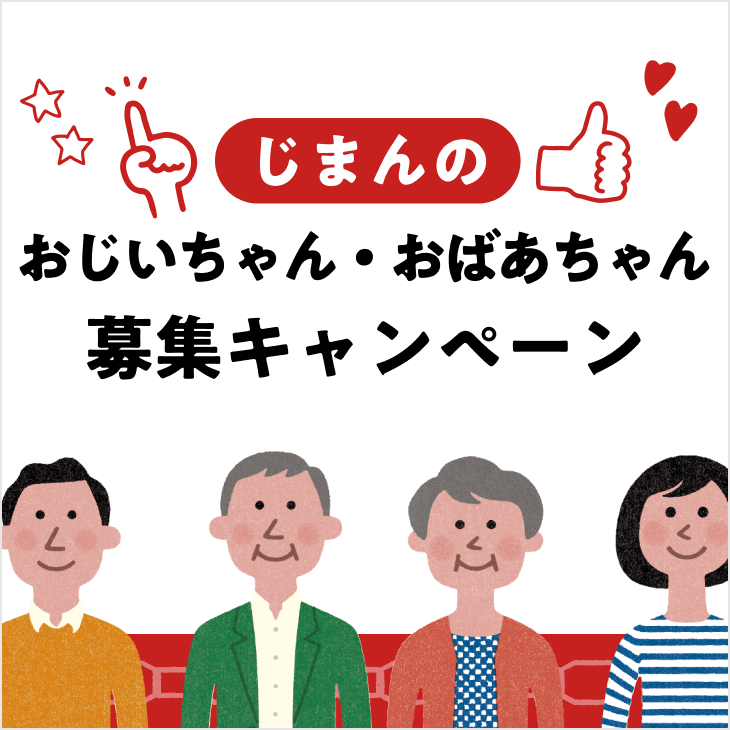戦場カメラマン・渡部陽一に聞く!【後編】いつでもどこでも犠牲者は「子ども」なんです

前編のインタビューでは、戦場カメラマンになったいきさつや、国際関係のなかでなにが起こっているかを知るには、視点の「柱」を複数持つことが重要だと語ってくれた渡部陽一さん。
後編のインタビューでは、仕事上、あるいはプライベートのうえで、これまで経験していたターニングポイントについて、話を聞いていこう。
最後に興味ある話題として、戦場カメラマンという職業をリタイアした後の人生観について、年をとっても元気に生きていく手段についても話を聞いてみた。

- 渡部陽一(わたなべ・よういち)
1972年生まれ、静岡県富士市出身。学生時代から世界の紛争地域を専門に取材を続ける。戦場の悲劇、そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け、極限の状況に立たされる家族の絆を見据える。イラク戦争では米軍従軍(EMBED)取材を経験。これまでの主な取材地はイラク戦争のほか、ルワンダ内戦、コソボ紛争、チェチェン紛争、ソマリア内戦、アフガニスタン紛争、コロンビア左翼ゲリラ解放戦線、スーダン、ダルフール紛争、パレスティナ紛争など多岐に及ぶ。

戦場に生きている人々の
「日常」を伝える使命に気づいたきっかけ
戦場カメラマンである渡部さんにとって、最大の転機となる出来事はなんでしょう?
渡部
僕にとっては、やはりイラク戦争が、それになります。30代の入り口にはいったばかりのころですね。
20代のころの僕は、誰よりも早く前線に向かい、衝撃的で刺激的な写真を撮ろうという野心に燃えていました。前線での激しい銃撃戦、市街戦、テロ現場での爆発のシーンなど、危険な場所に自ら出向いて、むごたらしい殺戮が行われている事実の証しとなる写真を撮ろうとしていました。
ただ、そのような無茶を繰り返したおかげで、銃をつきつけられてパスポートを盗られたり、カメラを盗られたり、ケガや病気で立ち往生したり、さまざまなトラブルにしばしば巻き込まれていました。
危ない場所に行くのが戦場カメラマンの仕事ですから、危険な目に遭うのは覚悟のうえだったでしょうね?
渡部
ええ、そうですね。最初は、そんなふうに、自分の仕事をとらえていました。
そんなとき、イラク戦争の取材で、ある家族と出会ったのです。
僕は戦場取材をするとき、必ず現地の人に通訳やガイドをお願いしているんですが、そのガイドのひとりの家族でした。取材期間中の数カ月、一緒に生活を共にしていると、イラク人の家族がお互いを支え合っている様子をつぶさに観察することができたんです。
子どもたちを守ろうとするお父さんとお母さん。そんな両親を大切に思う子どもたち。親子がやさしく寄り添い、戦時下の悲惨な環境のなかで、ささやかな日々のしあわせを大切にしていました。
そのやさしさは、家族に対してだけでなく、同じ境遇にある隣人や友人にも向けられていました。米軍の爆撃によって病院を失い、学校などを失った厳しい環境のなかで、生きていくうえで必要なものがあれば、対価を求めず、惜しみなく隣人や友人に分け与えていました。
ケガをした子どもがいれば、その子を救うことが最優先になります。
お互いを支え合うことが、戦時下における生きる術(すべ)になるんですね。
渡部
はい、そうです。お互いを助け合う精神の土壌が、すでにイラクの人たちには備わっていたように僕には見えました。それは、古代メソポタミア文明からつながる、長い、長い伝統によって培われたものです。
そんな彼らの姿に感動し、リスペクトした僕は、単に戦場のすさまじさ、悲惨さを強調するだけでなく、戦時下に生きる人々の日常を伝える写真を撮ることこそが、自分の戦場カメラマンとしてのテーマなのではないか、と思うようになったんです。
それは渡部さんにとって、大きな変化だったでしょうね。
渡部
その通りです。戦時下であっても、人々の日常が隣合わせにあって、お互いがそれぞれ支え合って生きている。その特徴はイラクだけでなく、ふり返ってみれば過去30年間で取材した世界各国の戦場に共通する特徴でした。
これまで13回も訪れているウクライナでもそう、イスラエルのガザ地区でもそう、戦時下での何気ない、普通の日常がそこにありました。そんな、ある意味では逆説的にも聞こえる「日常」を伝えることが、僕の使命であることに気づいたのです。

紛争や戦争の犠牲者は、
いつでもどこでも「子どもたち」なんです
でも、戦時下に暮らしている人々の「日常」には、ケガ人や死者が出たりと、悲しい場面に直面することも多いのではないですか?
渡部
おっしゃる通りです。僕が戦場カメラマンとして、世界各国の紛争地を訪れて感じたこと、それは、戦争の、犠牲者は、いつも、「子ども」たちであるということでした。
それは、銃によって撃ち殺される、爆撃によって命を奪われる、ということだけにとどまりません。軍が去ったあとにも彼らが地面に埋めた地雷にやられる、化学兵器の影響で重篤な病気になる、戦争により発生した飢餓で飢え死にする、といった「第二の戦争被害」と呼ばれるもので多くの子どもの命が奪われているのです。
僕が戦場下の現地だけでなく、戦争が終わって、国が復興していくところにも取材しているのは、そうした様子を世界に、そして日本にも伝えるためでもあります。
そのような悲しい現状を前にして、渡部さんはどんな態度で取材をしているのですか?
渡部
あるとき、こんなことがありました。
銃撃を受けた小さな子どもが、避難所の病院に担ぎ込まれ、お医者さんによる懸命な処置が行われている場面に直面したのです。その子どもの両親は、半狂乱になって「我が子の命を救ってほしい」とお医者さんに訴えかけていました。
このとき、僕はその場の様子を撮影することはできないと判断して、病室を出ました。
戦場で取材をする戦場カメラマンには、大きな葛藤に直面することがしばしばあります。それは、撮影する被写体、特に現地の人が兵士に銃口を突きつけられた場面などにそれを「撮るべきか?」、それとも「その人を助ける行動をすべきか?」というジレンマです。
でも、自費で戦場に赴いた戦場カメラマンにとっては、あえてそのようなショッキングな写真を撮ることを優先しそうに思えますが?
渡部
ところが、僕を含め、今まで僕が接してきた世界各国の戦場カメラマン、ジャーナリストたちは迷いなく、「記録よりも目の前の人の命を守る行動をとる」ことを選びます。
ですから、このときの僕は、瀕死の重傷を負っている子の写真は撮れないと判断しました。そして、病室を出て、事の次第を静かに待つことにしたんです。
すると、しばらくして病室から泣きながらその子どものお父さんが飛び出してきて、僕の手を引っ張ったのです。そして、「今にも亡くなろうとしている我が子の写真を撮ってくれ。その姿を国外にいる人に発信して欲しい」と涙ながらに訴えてきたのです。
戦時下の国では、指導者による強権的な言語統制が敷かれていて、自国民が国外に戦争の悲惨さを伝えることは、ほぼ、不可能です。
だから、外国人である僕に、自分に替わってそれを伝えてほしい、そのお父さんは、そう僕に頼んできたのです。そのお父さんの、悲痛な訴えに背中を押されるようにして、僕はシャッターを切りました。
実はこういう状況は、テロの現場や戦場ではよくあることです。犠牲となった家族や友人の遺体の写真を撮ってほしい、お葬式で家族が泣きじゃくっている姿を撮ってほしい、と。
そうした願いに応えるたびに、僕は、戦場カメラマンとしての使命を強く感じます。

自身が家族を持ったことで、
自分の意志がより強固なものになった
渡部さんは2009年、36歳のときに結婚をして、自分の家族を持ちましたね。命を危険にさらす戦場カメラマンにとって、これは重大な決断なのではなかったですか?
渡部
もちろんです。僕の人生における、もっとも重大な決断でした。
前編のインタビューで、食えないころの僕がバナナの積みおろしの仕事をして、海外への格安航空券を手に入れていた話をしましたね。
家族をもった以上、そんな生活に戻ることはできない。どんな手段を使ってでも、家族を守る、支えていく。その決意が、僕の人生の、不動の柱になりました。
妻は、僕が危険と隣合わせの仕事をしていることを覚悟の上で、僕との結婚を承諾してくれました。その気持ちを、絶対に裏切ることはできないと思いました。
そして、その決意は、翌年に長男が生まれたことで、さらに強いものになりました。
守らねばならない存在が大きくなったことで、不安になることはありませんでしたか?
渡部
いえ、ありませんでした。むしろ、責任が重くなればなるほど、心の底から元気がみなぎってきました。
戦地に住んでいる家族のお父さんの気持ちを、我が身に照らし合わせて理解できるようになったことも、僕にとってはとてもうれしい、大きな変化でした。
戦場カメラマンは海外で過ごすことが多いと思いますが、子育てや家族サービスはおろそかになってしまいませんか?
渡部
確かに、独身だったころの僕は、1年のうち10カ月くらいのペースで、海外に身を置いていました。
でも、結婚してからは、海外にいる期間は、多い年でも4カ月程度になりました。しかも、その4カ月は行きっぱなしの4カ月なのではなく、行っては帰り、行っては帰りの4カ月なので、通算すればもっと短いかもしれません。
そうすることができるようになったのは、戦場カメラマンとして積んできた経験のおかげです。
現地のガイドや通訳をお願いする方とのネットワークが世界のあらゆる国にできたので、彼ら彼女にから情報収集しながら計画をしっかり立てられるようになったのです。
行き当たりばったりの取材ではなく、効率よく、スピーディに計画した通りの取材ができるような体制が整ってきたのです。

テレビの報道番組ではなく、
バラエティ番組に出演する意義とは?
ところで、結婚してしばらくしてからのころ、渡部さんはテレビのバラエティ番組によく出演するようになりましたね。どんなきっかけがあったのですか?
渡部
TBSの『笑撃!ワンフレーズ』という番組から出演のオファーをいただいたんです。
2009年の終わりごろでしたから、ほぼ結婚と同時期になりますね。
探偵さん、バーテンダー、引っ越し屋さんなど、さまざまな職業を持つ人の裏話を聞くというコーナーで、戦場カメラマンとして登場してほしいということでした。
報道番組ではなく、深夜のバラエティ番組に出演することに葛藤はありませんでしたか?
渡部
「出ていいものだろうか?」という思いは、確かにありました。そこで、僕の師匠である、報道写真家の山本皓一先生のご自宅を訪ねて、ご意見を聞いてみました。
すると先生は、ほぼ即答で、「陽一、出ろ」とおっしゃいました。
戦場カメラマンの存在を世に知ってもらう、いい機会じゃないか。もし、自分に向いていないと思えばやめればいいし、できそうだと思えば、やってみたらいい、というわけです。先生のその言葉をいただいて、初めて僕は、「腹をくくってやってみよう」という気になりました。
その結果、渡部さんはその独特な話し方とキャラクターが評価されて、他のバラエティ番組でも引っ張りだこの人気者になりました。そのことについて、どのように考えていますか?
渡部
それは、自分にとって、とてもよいことだったと思っています。
最初は、24時からの深夜番組でしたけれども、次に呼ばれたときには22時になり、19時のゴールデンタイムになり、ついには12時のお昼の『笑っていいとも!』という国民的な人気番組にレギュラー出演をするようになっていました。
そうなることで僕は、お茶の間でごはんを食べながらテレビを見ている日本の子どもたちが、戦場カメラマンである僕の姿を目に留めて、さまざまな疑問を抱いてくれる可能性に気づいたのです。
その可能性とは、こういうものです。テレビを見ている日本の子どもたちが、お父さん、お母さんに向けて、こう質問している光景を思い浮かべたのです。
「テレビに出ている、あの、ベレー帽をかぶっている、ヒゲのオジサンが話している『イラク』とか『ウクライナ』とか『イスラエル』ってどこにあるの? 『戦争』って、どうして起こるの? 日本は『平和』な国だというけど、本当にそうなの?」と。
確かに渡部さんがテレビのバラエティ番組に出演することで、そんな場面が日本全国のあちこちで起こっているのは容易に想像できますね。
渡部
僕は、今回の本『晴れ、そしてミサイル』のなかで、「平和とは、やりたいことを自由に選ぶことができることです」と述べました。そういう意味で、日本で暮らしている子どもたちの多くは、例外はあるけれど、平和というものを享受しているのかもしれません。
でも、戦場で暮らしている子どもたちはほとんど、やりたいことを自由に選べないのです。
生きるために必要な住居や水、食べ物もなければ、社会的な営みをおくるための環境インフラも破壊されてしまっている。
そうした現実が海の向こうのさまざまな国にあるのだということを、同世代の日本の子どもたちに伝える手助けができるとしたら、それは僕自身、大いなる意義のあることではないかと思うんです。

年をとったら海外の高齢者のように
好きな場所で好きなことをする「自由」を満喫したい
最後に質問です。先進国のなかで日本は、いち早く高齢化を迎えています。海外経験の長い渡部さんが感じる、日本の高齢者と海外の高齢者の違いはありますか?
渡部
僕が大いに感じている違いは、その人生観、というか仕事観のようなもの、でしょうか。
実は、僕が出会った、海外で仕事をリタイアした高齢者の多くは、実に活き活きとしています。まるで、仕事をしていたころの自分は仮の姿で、リタイア後の自分こそが本当の自分なんだと思っているかのように、待ってましたとばかりに好きな土地に旅に出かけます。
そういう人の共通点は、おしゃれだということ。別に高価で華美な服装をしているというわけではありません。ただ、キチンとして、会う人に清潔感を与えるような服装で旅をしています。短期ではなく、長期に渡る旅なので、滞在先の土地の文化や人になじむための知恵なのでしょう。
では、渡部さんもお子さんが成人して、ひとり立ちしたら、そのような旅に出たいと考えているのですね?
渡部
即刻、出発します。
地球のうえを何周も、グルグルとまわりたいです。世界中のビーチを訪れて、子どものころからの趣味だった釣りを楽しみたいし、友人、知人に会いにいくのもいいですね。
おそらく妻は、妻なりのリタイア人生を考えているでしょうから、「一緒に行こう」なんて強要しないで一人旅になるでしょう。
戦場カメラマンとして、紛争地や戦地で命を落とすのは不本意なことなんですね?
渡部
それは、絶対にあってはいけないことだと思っています。僕が紛争地や戦地に行ったとき、第一に優先するのは「生きて日本に帰ってくること」です。
そのために、特ダネになる写真が撮れそうな場所でも、ガイドさんが「ここより先に行っては危険」と言った場所には決して立ち寄りません。必要な場では身を引く。それもある種の「勇気」だと思うからです。
それは、先ほど述べた、戦地で人が危険にさらされるのを見たとき、「撮るよりも助ける行為をする」という優先順位と同様、「生きて日本に帰ってくること」は不動の選択です。
いやぁ、今から楽しみですね。自分の好きなように、好きな国、好きな場所で自分の時間を自由に使えるようになる日が。その日のことを想像すると、張りのある毎日を過ごすことができるような気がします。
興味深いお話、どうもありがとうございました。
渡部
いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。

渡部陽一の渾身のエッセイ 『晴れ、そしてミサイル』
ディスカヴァー・トゥエンティワンより好評発売中!
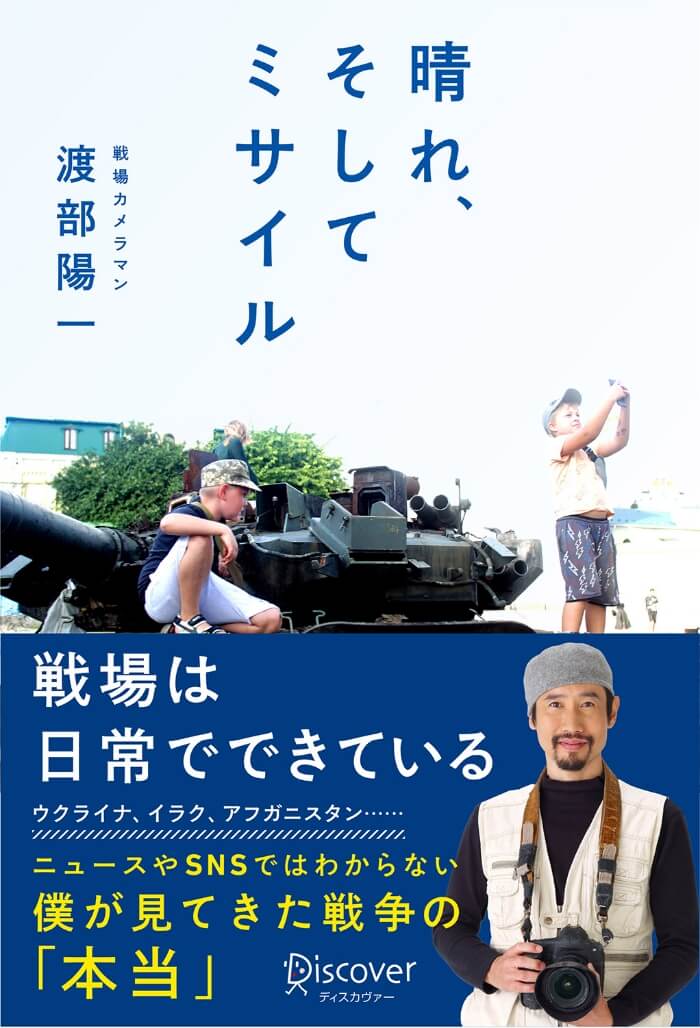
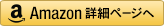
- 著者: 渡部陽一
- 出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 発売日:2023年10月20日
- 定価:1,760円(税込)
ウクライナ、イラク、アフガニスタン……
戦場カメラマン、渡部陽一は、
約30年にわたって世界の紛争地を取材し、
そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾けてきました。
本書は、そんな渡部陽一だからこそ描ける、
いち個人の視点、生活する人々の視点から
戦争や平和について考えていく一冊。
戦争下にあるウクライナの街の様子、暮らしから
世界中の紛争地で見てきた光景、
そして、SNSが変えた現代の戦争の姿、
一方で、SNS時代だからこそ、ぼくたちができることまで、
「今だからこそ知っておきたい」戦争の「本当」の姿を描いていきます。
この記事について報告する